本業では無いので、そこまでお金はかけてません。
でもまあ自己満足できる程度のものは作れる環境は
できるので、ちょっと参考になればと思います。

最近ちょっと大丈夫かっていうほど
モノの入れ替えが激しいのですが
KAOSS PAD買ってしまいました。
てか今こんなの出てたんですね、知らんかった。
昔KP2は持ってたけれど、当時MTR付きのサンプラー(SP808)で
曲を作っていたので、シーケンサーのフレーズを
全部流し込んだあとにエフェクトかけるのとか無理。
しかもSP808のエフェクターもかなり優秀だし、
とかいうことでほとんど使う機会がなく手放してしまいました。
だいたいタッチパッドていうのが操作が難しい。
変なとこ押しそうになるし。ツマミの方が確実やなとも思っていました。
で、時は移って2013年、最近はSPINで遊ぶことが多いのですが
ちょっとフィルターとディレイくらい欲しいなあと思ってきたわけです。
ディレイくらいならdjay付属もあるけどどうにもイケてない。
で、見つけた。
しかも安い。
12800円。
買うでしょ!!
ちなみにKP3でも16800円だと。
昔は2万オーバーだったよねぇ、確か。
で、このKAOSSPAD QUAD 何が良いかというと
エフェクトが複数掛けられる。
一応4つパートが分かれてて
ルーパー系、歪み系、フィルター系、空間系になってて
その中でそれぞれ5つのエフェクトが存在。
で、4パートは複数同時にかけられる。
でもよく考えると、エフェクト4つ出来てもコントロールはパッドのみ
いっぺんにコントロールできないじゃん!!ってなるのですが
さすがよく考えられてます(何が)。
一応、組み合わせた時のエフェクトのそれぞれの掛かり具合はチューニング
してあるそうです。ですので全く変なことにはならないです。
あと、リバーブはこの位置で、あとはフィルターを動かしたいとか
いうのもありそうですが、そういう時は
パート毎にFREEZEボタンってのがあって、押したパートのエフェクトのパラメーターは
動かさないという設定ができます。
難を言うと、FREEZE解除した時に指どこに置いてたかわかんなくなる事がありますがねw
あともう一個いいところが、エフェクトの数の少なさです。
KP2を使ってた時は、正直エフェクトのバンクの多さでうんざりでした。
全部ディレイ聴き比べてみたりして、だんだんわかんなくなっちゃって
とかいうのがありましたが、さすがにこんだけ少ないと悩む余地がなくて良いです。
あとデザインがカッコイイ。
今までのカオパはちょっとダサかった。
今回のは割りとスッキリしたデザインでカッコイイ。
昨日ちょっとだけダウナー系のテクノで使ってみたけど
めっちゃ楽しかったです。

MC-303から入った自分としてはMPCってなかなか馴染めない。
サンプリングからってのがめんどくさい。
音源いじって作ればいいじゃんと思って使ってない。
ステップシーケンサーとしても使いづらいし
あの液晶でちまちエディットするのがめんどくさい。
でもやっぱりカッコイイ。
自分の時はMPC2000XLが出た頃だったけどカッコよかった。
でもローランド派だったし、テクノっ子だったので
CO-FUSIONも使ってるってことでSP-808にしちゃった
あれは凄くいい機材だったので後悔はしていないけれど
もう今では扱われていないので、覚えた操作方法も活かせないし
やっぱりMPCにしておけば良かったかなあと今になっては思う。
で、まあそんな感傷はさておきとして
iPad版出てますよ、今はすこし安くなってるみたいなので今のうちに。
iMPC - Akai Professional

先日microKORG XL を買いました。
最近XL+が出たもんだから、安くなってるんです。
 ◆専用ケース(SC-MICRO-MSG-RD)付!microKORG誕生10周年記念!限定プレミアム・カラー・モデル... |
 microKORG誕生10周年記念限定カラー・モデル!【数量限定ソフトケース付き!】KORG コルグ micro... |
確かにこの限定カラーは惹かれますが
じゃあそれと音色のアップデートに2万の付加価値を払うかと言われると
むしろ値下げしたのに飛びついたわけでした。
 【限定タイムセール】●KORG microKORG XL 【限定タイムセール】 |
やっぱりハードのシンセはいいですね、音が良い、音作りが楽しい。
R3だと僕の愛機MS2000の音色パッチもあるとの事で相当悩みましたが
じつはこの機種にも提供されてました。
しかし最近のは凄いですね。
USB接続出来るし、KORGからエディタが出てて
PCから音色のエディットも出来る。
ってそれだとソフトシンセと変わらんやん!!って思いましたが
これの凄いのはソフトで選んだ音色がハードで鳴らせるってところです。
先ほどちょっと書きましたが、エディタの付属で付いてくるプリセットサウンドが
初代microKORG, microKORG XL, MS2000, MS2000B の音色があって
それも自在に呼び出せるんです。ハードの中に取っとかなくてもいいという。
(必要な音色だけ取りましたが)
ちなみにXL+のエディタはXLでは使えません。当然パッチも。
ここらへん融通利かせてくれたらいいのにKORGさん。
XL+のプリセットサウンドはUK版とUSA版があるようです。
あと、オーディオインターフェースも小さいのに替えて
(今はALESIS PHOTON X25 (デカイ))
とかしたらELECTRIBEもまた使えるかな、とかそんなこと考えてます。
最近、ようやくDAWにも慣れてきて、また音楽づくりが面白くなってきています。
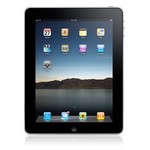
iPadというか、タブレットPCの存在意義がよくわからなかったので、
特に興味も無かったのですが、FFが出てプレステが世に広まったように(古いか)
アプリによって、ハードの普及ってかわりますよね。
っていうのが、今回ヤラレてしまったのがこのアプリ
KORG iELECTRIBE
90年代後半に、2音シンセのみのEA-1、リズムマシンのER-1、
サンプラーのみのES-1、PCM音源で一通りそろえたEM-1と
大胆に機能を切り分けて発売され、大ヒットを記録した
ELECTRIBEシリーズのiPad版がリリースされました。
ラップトップの機材の特徴だった、「手でパラメータを弄くる」
というのが、iPadだったら出来るんですよね、たしかに。
iPhoneだと小さすぎるし、これはすごいかも。
しかも今は初回限定価格で1200円(後日は2300円になるとか)とか。
これはかなり迷いますね・・・
KORG iELECTRIBE へのリンクはコチラ

とうとうmp3プレイヤーもエフェクターになりました。
コンパクトMP3プレイヤー MUSICIAN LIVE MATE LM3
今までもその場で録音するRC-20XLとかJamManとかあったけど
mp3プレイヤーって初かも。
これでバンドメンバーのいない人も
ライブハウスの人にカラオケ流してもらわなくても出来ると。
ってかそうしちゃうと全部ギターアンプから音出るだろ!!
物欲的には惹かれるけれど
イマイチ使い道が謎。
CDとかMP3の数はハンパじゃないんです。
で、それなりにですがギターとか弾けて
DTMで曲作ったりもできるんです。
そんな僕がまともにできないのがドラムとDJ.
打ち込みやってるし、テクノとかヒップホップとか
好きなんだから、DJも出来るんでしょ的な事を
たまに言われたりもするのですが、
これが全く出来ないんです。
でもですね、憧れはあるんです。
とはいえ人にお披露目するようなこともまず無いので
びみょーな感じなんですね。
(以前CDJを二台買ってみたが、あまりパッとせずに
すぐにあきらめた経験あり)
でもやっぱり捨てきれないDJへの憧れ。
ってことで、今度はPCでやってみようかなとか
おもったりするわけです。
PCDJのいいところ
・音源をさがすのがラク
・ケーブル類が散らからない
・波形を見ることができる
・(ソフトによっては)ミックスを手軽に録音できる。
・二枚使いが簡単(ファイル一個でいいので)
・場所をとらない
PCDJの悪いところ
・見た目あんまりすごくない
・7インチのレコードがかけられない
・音がレコードと比べると悪い(はず)
なんてとこがあると思うんですね。
でももう私もアラサーですし、今頃から
バトルDJばりにズキュズキュこするわけにも
いかないんで、大人な感じでさらっと
ハウスでも流しときゃいいかな、とか思うんですよ。
で、ソフトもなんか色々ありますが、
とりあえずハードの方が大事かな、と思っております。
とりあえずよく見るのが
VESTAX VCI-100

なんかプチターンテーブルセットみたいな感じで
かわいいですよね。
ただ、これはオーディオインターフェースが付いてないので、
別途A/Iを買う必要があります。
なんでA/Iが必要かというと、PCから出る音は
ちょうどモニターの音になってしまうみたいです。
だからA/I通して出してあげないと、モニターで
ピッチあわせてる音がそのまま入ってきちゃうという。。。
で、オーディオインターフェース込みだと
VESTAX VCM-100

これはタンテもどきと、タテフェーダーがついてません。
ハウスとかのロングミックス向きみたいなので
ヒップホップとかには向かないと思います。
でもこれってデザインがすっきりしてていいですよね。
で、タンテもどきがついたオーディオインターフェースつきのは無いのかというと
VESTAX VCI-300があります

ただしこれはお値段倍以上しますので却下。
割と庶民派向けのVESTAXでも結構な値段するじゃんかとか
思ってましたら、やってくれます、本当の庶民の見方
べリンガー
BCD3000

VCI-100よりも1万円ほどお安くなった上にオーディオインターフェース付き。
操作性もレビューとか見てたらなかなかのものみたいです。
他にもNUMARKとかも安いのは出してるみたいですが
あんまり評判良くないみたいです。
とりあえずはBEHRINGERにしとくかな・・・
あ、ちなみにどのハードもバンドル版のDJソフトが入っているので
買ったその日から遊べます。

やっぱりいても経ってもいられなくなり、
とりあえず一通り購入、検証してみました。
sony MDR7506と AERIAL7 TANK
 VS
VS 
モロにスタジオユースな外観のMDR7506とTANKとの比較をしてみました。
まあ値段が倍ぐらい違うのですがw
音はそれぞれ。
MDR7506はモニターにも使えるような
キッチリとした音が出るのに比べて
TANKは低音出すぎですw
というかAERIAL7のものはどれも低音強め。
装着感はTANKの方がすっぽりという感じでいいです。
あとiPhoneマイクが付いてるのでリスニング中の
通話も問題ないです。
でもこの季節にこんなデカイのつけてたら
重いし、蒸れるし、使えたもんじゃありません。
結論、聴き方しだいではどっちでもアリかと。
リスニング用としてならおそらく好みかと。
AKG K24Pと AERIAL7 MATADOR
 VS
VS 
中量級ヘッドフォン対決
これはAKG K24Pの圧勝かと。
音がクリアだし、見た目もそこそこカッコイイし付け心地もよくとてもバランスがいい。
(たしかauのコマーシャルでも使われたよね)
MATADORも見た目と付け心地はいいんだけど、やっぱり低音強すぎ。
ちなみにK24Pは今はディスコンでこのK420ってのが
後継機だそうです。値段は倍くらい違うと思いますが。

ゼンハイザー CX300 VS AERIAL7 SUMO
 VS
VS 
これもなかなかいい勝負
CX300は音がクリアでカチッと鳴ってる感じがしますが
(それでも低音がこもり気味と良く言われてるみたいですが)
SUMOはブンブン低音が鳴っててこれはこれで気持ちいい。
音がラウドなのも好印象。
オールマイティにいけるのはCX300でしょうが
エレクトロやヒップホップなど、聴くジャンルによっては
AERIAL7もあると思います。
SKULLCANDYのイヤフォンはポイントがいまいち見つけられなかったけど、
AERIAL7は低音とラウドさが重視されてる感じで
わかりやすくていいかもしれません。
あとどの製品にもiPhoneマイクが付いてるのがポイント
(TANKとMATADORはマイク無しケーブルも付属)
まあ我々くらいのアラサー世代はあんまりカラフルな
ヘッドフォンはつけづらいもんがありますが。
ミニ鍵盤のシンセサイザーながら音の太さ、自由度
ボコーダー機能等で大絶賛をあびたmicrokorgの
後継機種、micrKORG XLが登場。


このエレピっぽいデザインがたまりませんね。
初代マイコルもレトロな感じで良かったんですが、
相変わらずデザインがカッコいいです。
僕はシンセの機械の仕組みがよくわからないのですが
初代マイコルがms2000を元にしているのに対して
今回はradiasを元にしているそうです。
ms2000

radias


でもKORGがフリーで配布しているソフト使えば
MS2000の音も再現できるそうですw
で、あと改善点といえば、鍵盤が良くなった(らしい)点
意外とライブなどで使われてるのをみて、もっと良くしようと
今回は鍵盤にかなり力入れたみたいです。
すごいですコルグ。職人やと思います。
プロジェクトXみたいです。
今回はusbも使えるのでMIDIキーボードとして
使えるのもポイント高いですね。
ちょっとお高いのが難しいところですが
これはガジェットとしても欲しい一台です。
ちなみに初代microKORG


音楽的欲求が高まって、作曲をしているのですが、
ちょっとボーカル録りがしたくなったので、
マイクを調達することにしました。
はじめは前に紹介したSHUREのSM58にしようかと
思っていたのですが、色々見てたら、
見つけたのがこれ、BEHRINGER ULTRAVOICE XM8500

評判みたら、なかなかのもの
素人からすると、SM58とも勝る劣らずとのこと。
しかも値段が3000円!!
すごいです。SM58の値段で4〜5本買えちゃいます。
どうせ歌唱力も無いし、エフェクトもかけるからってことで、
こっちのマイクにしました。なかなかのいい買い物でした。
ちなみに便乗して、卓上スタント、ケーブル、ウインドスクリーンも
購入。合計しても1万円切ってますw



様々な楽器が入っています。
ピアノやストリングスの音なんかも入っていて、
割と使える音だったりします。
ところがソフトやシンセがどれだけ進歩しても、
ギターの音だけはなかなか実用に堪えないところです。
確かにギターの音ってピッキングひとつでも音の出方が
違うし、コードの弾き方も色々あるので、
シミュレートするのは難しいと思います。
で、DTMやっててギターの音が欲しいなと思うとき
どうするかっていうと・・・
ギター弾いて録音するのが一番です(笑)
フレーズ弾いて録音して、ぺっぺっと貼付けて行くのが
一番効率いいですね。
で、その録音方法ですが、スタジオでやってるみたいに、
アンプにマイク何本かたてて・・・とやるのは
資金的にも住環境的にも無理がありますよね。
で、その際に必要なのがアンプシミュレーターというわけです。
アンプの役割については後述します(どうやら何かあったらしい)
僕も3つしか使った事ないので、あれですが、
とりあえず定番として有名なのが、LINE6 POD
最新版

一個前のバージョン

ベース用

コンパクト版

まあ、定番ということで、安定した音作りができるんですが、
個人的には音がゴリゴリしすぎているかなあという感じがします。
そして、僕がイチオシなのが、vox tonelab
音に艶がある感じがします。歪み系の音も柔らかいですしね。
ギンギンに歪ませたい時はpodの方が良いと思いますけれど。

最近はペダル付きで安いのも出てるみたいですね
ペダルついてると机の上で作業出来なかったり
色々不便そうですけど、ライブで使いたい人は
こっちのがいいかもですね。

あと、今出張中なんですが、ついついギターを買ってしまい、
とりあえずということで買ったアンプシミュレーター
Digitech GENESIS 3
これがなかなか使い勝手が良い



上記の2種にくらべて、かなり安いです。
こっちは新品

音が若干デジタル臭いとの話しも聞きますが、
そこまで気になる感じも無く、なかなかいい感じでした。
価格帯、音の質感など色々ありますが、
結局はどういうギターの音を出したいってのが重要で
その辺は試奏するのが一番ですが、そうもいかないよって人は
ちょっとこのブログなど参考にして頂けたら幸いです。
ちなみに、なんでアンプが大事なのかということなんですが、
先ほどアンプシミュレーターのところで書いたように
モノによって出音が変わってきます。
ギターも大事なんですけれど、アンプがショボかったら
台無しです。
スタジオ行ったら大体マーシャルとかジャズコは
置いてあるので、大丈夫ですが、家ではあんなデカイアンプ
置けませんからね・・・
まぁちなみにマーシャルはこんなの
ゴリッとした音が魅力



ジャズコ(ROLAND ジャズコーラス)はクリーンで
エフェクターが乗りやすいのが魅力



あとはアシッドマンが使ってるORANGEとか




値段的に手頃なのがVOX



これ、なかなか良いです。
割と地味な感じのエフェクターの紹介でしたが、
今回はもう少し飛び道具的なエフェクターを紹介します。
まずはディレイ
ディレイというと、その名の通り、音がちょっとずつ
遅れて聞こえてくるやつですね。ダブなんかでよく使われますが、
エレクトロニカなんかでも、ステレオでかけてあげると
ちょっと雑な打ち込みしてても、細かくエディットしてるように
聞こえてきます(笑)
EVENTIDE TIMEFACTOR

これはまだ使ったことないのですが、デザインがカッチョ良すぎる。
かなり複雑な設定もできそうで、音も良さそうです。
ちなみに姉妹品、こちらはMODエフェクター
フェイザーなどが入っています。
EVENTIDE MODFACTOR

LINE6 DL4

これはずっと前から欲しいと思っているディレイ。
人が使ってるのを見て、惚れました。
ちなみにこれはギター用ですが、DTMでも全然いけます。
ギター用といえば BOSS DD-6

あと僕が使ってるのは IBANEZ DE7

これは良いです。なんといっても
ディレイの繰り返し回数を設定できるのがいい。
ディレイってだんだん小さくなりながら
「ぴゅーん、ぴゅーん、ぴゅーん」となり続けるのですが、
これは設定で、2回で止める、ということが出来ます。
これって、オークションで買ったエフェクターのセットに
まぎれてたものなんですが、思わず気に入ってしまい、
今ではギター用ではメインのエフェクターになってます。
あと、ラック系でいくと、アートリンゼイも細野さんも
テイトウワも使っているというZOOM STUDIO 1201

※中古品なのでお早めに
これはもう中古でしか手に入りませんが、良いエフェクターです。
ディレイのほかにもリバーブやらなんやら入ってます。
これの音をロウファイにしてくれるのが実はお気に入りです。
その他エフェクターといいながら、ディレイの話題だけで
これだけなってしまいましたね・・・
じゃ、続きは次回ということで。
思いますが、スペース、予算的にもお手軽なシステムで
やるのもありだと思います。
出てから非常に売れているKORGのKAOSSILATOR
これ一台で、一曲できるってくらい

ただ、これ記録できないから、ライブっぽくなってはしまうのですが
それはそれで、アツいと思います。YOUTUBEなんかで演奏しているのを見ると
俺もやりてぇ!!って気持ちになること間違い無しです。
値段は2万円前後です。これだけ遊べてこの値段だったらこれは間違いなく
買いだと思います。
KAOSSILATORにもリズムは入っているのですが、どうしても
エレクトロロッキンビーツというか、テクノっぽい感じは
否めません。もうちょっとファットなビートがいいんだけど
って方には、AKAIのXR20なんかが別にあるといいと思います。

値段が約3万円くらいなんですが、MPC500で約6万くらいと思うと
ちょっと安めです。リズムマシンで、サンプリングは出来ないのですが、
実際リズムはプリセットで、上モノは手弾きが多い自分としても、別にこれで
いいのかなぁとか思ってしまったりします。
まだ音は聴いていませんが、音質を大事にするAKAIなので
そこは大丈夫だと思います。
んで、エフェクターが別に欲しいなぁと思ったら
KORGのMINI KP
売れに売れまくっているDJ用エフェクターかKAOSS PADの
ミニバージョン。

僕も昔KP2持ってましたが、実際に録音する時には使う事無く、
どっちかっつーと遊び道具的な要素が強かったので、その割には
高いなぁと思って売ってしまったのですが、このくらいの値段なら
別にいいかなぁって思ってしまいます。
全部買っても総額6万くらいですかね、ライブを考えたりする方は
パフォーマンス的にかなり強いインパクトも与えられると思います。
あと、ライブの時に機材運ぶのがすごいラク。これ重要。
個人的なことなんですが、最近オーディオインターフェースが
欲しくなってきました。というのも今使ってるのは
ココで紹介しましたけど、MIDIキーボードの付属機能みたいなのを
使ってるんですね。
僕が作ってるのって、音質第一みたいなところがあるので、
とはいいながらもやっぱ趣味なので、そこまでお金をかけるわけにも
いかない、っていうのが現状ですが、やっぱそこそこはお金かけとかないと
どうにもならんよなぁってのがあります。
ってなわけで、ちょうどタイムリーにSound & Recordingマガジン
(略してサンレコ)が、audio I/Fの特集だったのでちょっと
付属のCD聞き比べてみたりしました。
ただここで対象のものって、たいがいが10万円オーバーのもので、
ちょっと僕には手の出しづらいものばかり。だから気に入ったメーカーの
ものの安いものでも手に入れようかなという感じです。
audio i/fって多少の違いはあれど、劇的な変化ってのはあんま無いです。
とりあえず僕の耳では。趣味で楽しむというのではあんまり気にしなくていいのかも。
とはいえ、このAPOGEE Ensembleは個性的でした。
あるいみちょっとオシャレな音、下手すりゃ下世話な音になりそうな。

僕が個人的にスネアの音が好きだったのがMARK OF THE UNICORNの896HD
いわゆるMOTUってやつですね、それが約20万くらいで、
それのちょうど半分くらいの値段で買えるのがコチラのMOTU 8Pre
あとエフェクトののりが良さそうとレビューされていた
T.C. ELECTRONICのSTUDIO KONNEKT 48
ただこれはもうちょい安いのがあります。
Konnekt 24D(約6万)
ちょっと高い(約7万)けど頑丈なつくりの
KONNEKT LIVE

ちなみにKONNEKT 8,24DがCUBASE SEが入ってるのにたいして、
KONNEKT LIVEには、Ableton Live Lite 6が入っています
ここらへんもちょっと選考基準に入れてみてもいいかもしれません。
ただこの辺は同時入力数が少ないという問題があります。
24Dとか12in12outとありますが、これはデジタル入力が含まれており、
普通シンセとかつなぐような端子は4in4outです。
4in4outといっても、ステレオだと2使うから、結局2台までしか
同時に入力できません。
そんなにいっぺんにやらないよ、って人ならいいんですけど、
MPCとELECTRIBE鳴らしながらシンセも弾きたい、とかなるともうアウトです。
てなわけで、じゃあ入力数が多いのってないのかなと調べてみるとありました。
FOCUSRITE Saffire Pro 10 i/o

これは26 i/oのものがサンレコに載ってましたが、
それの10イン/アウトバージョン。
実質デジタル除くと8 i/o
4つあれば結構足りそうですね。
FireStudio Project

これだと7万切ってます。こちらも8 i/o
これも特に悪い音とは思いませんでした。
まあこんだけ高いのじゃなくても、僕のインターフェースみたいに
やっすいのもあります。そんなんでもいいんでしょうけれど
音がいいとそれだけでもクオリティは上がります。
友達のバンド、ライブで見に行ってすっげカッコいいのに
自主制作で作ったCD聞いたらしょぼかった、なんてこと
ありませんか?あれは音が悪いからなんですよね、やっぱり。
スネアが鳴ってない、ベースが細い、などがおそらくカッコ悪い原因でしょう。
だから財布の中身と、必要なI/Oの数を自分の環境と照らし合わせて
選ぶのが一番いいんでしょうね。
ああ、お金ないからな、今年。
でもMOTUまではいかなくともKONNEKT LIVEくらいは欲しい・・・
って言うか最近、こんなのが出たようです。
 こっちの方が欲しい・・・
こっちの方が欲しい・・・
90年代後半くらいでしょうか、groove box と銘打ったハードウェアの
シーケンサーが一世を風靡したのは。
ROLANDのMC-303,MC-505、YAMAHAのRMX1、RS7000
KORGのELECTRIBEシリーズ、などなど、
今ではROLANDが細々とMCシリーズを出し続けているくらいです。
現行のMCシリーズROLAND MC-808

ちょっとお値段貼りますが、海外のメーカー
elektron machine drum sps-1

これは石野卓球、zonbie nationなんかも使ってるみたいです。
シーケンサーってのは、同じパターンで繰り返して
演奏させるための機械で、4小節なら4小節内で
打ち込んだ音を延々ループで鳴らしてくれるんですね。
で、そのループをいくつか作って順番に鳴らしていって
ソングを作ったりするわけです。
この辺はMPCも同じ機能を持ってます。
で、シーケンサーってのはY.M.O.の時代から存在していたのですが、
今までのと何が違うかというと、ROLAND MC-50に代表されるように
従来のシーケンサーは音源が入っていませんでした。
MIDIでシンセなどにつないで音はシンセから出したりしてたんですね。
昔はそんなMC-50で今のMC-808くらいの値段がしてたから、
いい世の中になったものです。
音源だけではなくて、MC-808見てもらったらわかるように、
ツマミであるとかフェーダーがついてます。
これで音をみゅいんみゅいんとか、しゅーーーーーんとか
出来るようになります。リアルタイムでライブ的なことができるんですね。
で、こういうグルーヴボックスがなんで廃れたかというと、
やっぱりソフトの方が色々拡張できるし、キレイに作れるし、とかいったところが
あると思います。
確かに「曲を作る」という点ではソフトの方が優れているかもしれません。
しかし、「音を楽しむ」という点では、ハードの方が断然良いと思います。
リアルタイムでディレイのツマミをはじめてひねったときの感動といったら。。。
あとは下で紹介してるKORGのEMX-1などだと特にわかりやすいのですが、
シンセやエフェクターのパラメータなどが実際にツマミ触ってどんな感じで変わるか
わかるってのがいいですね。
他にもステップ入力のやり方とか、その辺のしくみは一度体験しておいたが
いいと思います。特に4つ打ちものなんかはハードでやった方が全然楽です。
(慣れた人には別なんでしょうけど・・・)
で、もうひとつおすすめのシーケンサーKORGのEMX-1

こちらはサンプラー版のESX-1

これだとMC-808買うお金で二台買えます。
MPC持ってるなら、EMXとCDでも買えばいいと思います。
(MPCのサンプラーとはまた性格が異なるので、どっちも持ってても
面白いとは思いますが)
KORGはちょっと前まで、EA-1,ER-1,ES-1,EM-1などの
VAシンセ、リズムマシン、サンプラー、PCMシンセ・リズムと
単体もののシーケンサーを出していて、結構面白かったのですが
結局全部の機能を含んだこの2台しか残っていません。
でもこの2台も相当たのしいです。
今あるところだと、冒頭に紹介したMC-808かELECTRIBEかというところに
なるとは思いますが、電子音系(テクノ、ハウス、エレクトロニカ)だとELECTRIBE、
J-POP的なものとか、割と汎用的に使いたい、いい意味で無難な音色、
流行の音色って値段的にはMC-808でしょうか。ROLANDの音って、ちょっと
面白くないといわれるところはありますが、それゆえ何にでも使える強みは
あると思います。浅倉大介だってMC-505二台並べてましたからねw
ELECTRIBEはバキバキの過激な音も作れます、遊び道具的にはもってこいだと
思います。
前述しましたが、パソコンの前で、ディスプレイとにらめっこしながら
曲を組み立てていくのも楽しいですが、シーケンサーの前でノリノリで
つまみひねったりしながらグングン曲をくみ上げていくのはかなり楽しいですよ。
一晩たって聞くとがっかりすることも多いですがw
こないだはコンプの紹介をしましたが、次はイコライザーです。
イコライザーというとコンプよりも皆さんなじみがあるかもしれません。
普通にコンポとかにもついてますもんね、イコライザー。
ちなみにギターのエフェクターでもあります。
こんなの(BOSS GE-7)

普通のアンプとかと比べて、ちょっとツマミの数が増えた気がしますね。
DJミキサーなんかはHIGH MID LOWの3レベルだったりしますからね。
ちなみにラック版だとこんな感じです。
ツマミの数がハンパないです。

ちなみにこれで何ができるかというと、ご想像のとおり、
音の帯域を増幅、もしくはカットすることが出来るんですね。
シンセ音の高音がやたらうるさかったりとか、キックの音をもう少し
中域持ち上げたいとか、そういうのに使えます。
意外と劇的に変わりますよ。
とはいえ、元の音がキレイに出来てるのが一番いいんですけどね。
他の楽器、機材とミックスするとちょっとバランス悪かったりするときに
使うぐらいがいいと思います。
でも思いっきり中域だけありえないくらい上げるとかすると、
またそれはそれで面白い効果が得られたりします。
地味そうで意外に遊べるエフェクターかも。
てかもうべリンガーでいいじゃん安いし。

鳥の声を録りたくなったりすると思います(鳥の声はないか・・・)
そうなると、マイクが必要になってくるわけですが、
マイクも多種多様なメーカーがあったりして、
初めて買うときはどうすりゃいいんだと困ってしまいます。
まずはコンデンサーマイク。
こちらは音質もよくて、幅広く使うことができます。
スタジオ録音する時の歌録りなんかではこっちのマイクを使います。
これも値段はピンキリで、どれくらいのものを買えばいいのかと
思ってしまいますが、値段と質を考えると、
僕のオススメはRODEのコンデンサーマイクです。
RODE / NT-2A

ちょっとこれが高いなって人にはRODE NT3
僕はこっちを使ってます(あまりマイクでとらないので・・・)

ただ、コンデンサーマイクってのは電源が必要になります。ファンタム電源というのを供給できる
ミキサーであるとか、オーディオインターフェースが必要になってきます。
あと、吹きに弱いので、歌入れするときはポップガードが必要になってきます。
よくスタジオのボーカルブースにあるアレですね

って、これがいるってことはマイクスタンドが必要になってきます。
ギター弾いたりするかもしれないので、出来れば曲がるほうがよいです。

となるとコンデンサーマイクってお金かかっちゃうんですよね。
ってなところで便利なのがダイナミックマイク。
ラップするときはコレ持ってやったりしてますよね、
吹きにも強いし、特別電源がいるとかでもありません。
ダイナミックマイクといえばSHURE(シュアー)のSM58
よく「ゴッパチ」とか呼ばれたりしますが、その手のお仕事をしていない人が
こんな呼び方するとちょっと寂しいのでやめましょう。

レコーディングでも使ってる人は結構いますので、
こっち側で音録りするのも悪くないと思います。
なんといっても手軽に録れるのが良い。
他に最近ちょっと話題になっているのが、いわゆるフィールドレコーダーというもの
なんやかんやでSONYのが評判が良いみたいです。

歌以外の音だったらこういうのがいいかもしれません。
こんなので録った音を家で加工して曲にしちゃったりすると
ちょっとゲリラ的な感じがして ドキドキしますね。
ケーブルをつながない音を取り込むために使用するマイク。
何を録りたいかにもよりますが、専門に特化したものを選ぶか
ある程度使い回しの利くものを選ぶかが迷いどころですかね。
順を追ってDTM環境のところを紹介していこうと思ってたのですが、
あまりにも急なことでつい挙げちゃいました。
エレクトロプランクトンを超えましたね。
16ステップまでとはいえシーケンサーもついてるし。
問題はどうやって外部に出すかってとこですが
かなり遊べそうです。これでシンセとかシーケンサーの
基本がわかるかもしれません。
PCM、あるいはサンプラー、シーケンサーなどで曲を作っていくにあたり、
ステップ入力だけでは、ライブ感を出すというのは難しいところです。
シーケンサーというものは、8小節を繰り返し演奏するのには向いているのですが、
1曲まるまる4分間同じフレーズを繰り返すのではちょっと物足りないところです。
そういうのもあって、1パートくらい手で弾いたキーボードを入れてみるのも
手だと思います。多少ヘタッピであっても、編集できるのがDTMの良いところです。
じゃあ今回はキーボード、というかシンセサイザーの話です。
シンセサイザーと一口にいっても色々な種類があります。
まずはアナログシンセ。MOOGって聞いたことありませんか?
もしくはTシャツとか。MOOGってアナログシンセでは知名度が高いシンセのひとつです。

もう、見るだけで失禁しそうです。

キーボードなしなんてのもありますが、これはMIDIキーボードが
別途必要です。それでもこのラジオ基地みたいなルックスが
カッコよすぎる。
これは最近よく目にするREVOLUTION、なんともカッコいいですね。

音がぶっとくて、ちょっと不器用で、なんといっても見た目がよい。
しかし、値段がめっちゃ高い。欲しくなる気持ちはわかりますが、
このページを参考にしていただいているような方にはまずオススメしません。
ということで、お金のない僕らには、VAシンセというやさしいシンセがあります。
このVAとは、「バーチャル・アナログ」、つまり仮想的なアナログなんです。
パッと見、ツマミがいっぱいあって、アナログっぽいのですが、
中身はデジタルなんです。音はアナログになると若干細いのかもしれませんが、
とりあえず僕は気になりません。コンプかけたりして紛らわしましょう。
こちらはVAシンセでも有名なNORD LEAD
※でもこいつはMOOGばりに高い・・・

同じ赤でもお値段抑えめ、ALESISのMICRON

財布にやさしい国産KORGのmicroKORG
ミニ鍵盤ですが、音はぶっとい。
音作りが若干難しいですが。

こちらは一昔前に出たKORGのMS2000
僕はラック版のを持ってますが、

かなり音が作りやすいです。オススメ。

上記の2つはどちらも、電子音的なものがメインで、自分で音色を作るタイプの
シンセなのですが、「生音が欲しい」とか、「音色つくるのめんどくさいよ」って人に
オススメなのがPCMシンセです。
これはいろんな音をサンプリングして鳴らしているシンセです。
アナログやVAほどではありませんが、ある程度音色をいじることもできます。
ピアノの音なんかは、VAシンセで作るには難しい(どうしても電子音っぽくなる)ので
生音が欲しい方はPCMにするといいと思います。
こちらもピンキリありますが、5万くらいで買えるものでも全然良いと思います。
選ぶときは、自分がどの音が欲しいか(たとえばピアノ)決めて弾き比べてみると
いいと思います。ちなみに僕はセールで安かったという理由で決めました(笑)
もう高いシンセはいいやと思ったので、手ごろなPCMシンセ3種
何気に職人な音が人気の YAMAHA MM

僕が安さで買ってしまったROLAND JUNO-D
ROLANDってあまり好きな音ではないのですが、
意外に軽くて使いやすくてよい買い物をしたと思ってます。

にくい迷彩のあんちくしょう KORG X50(これでも限定)

この辺ですかね、サンプリングで足りない部分を補ったり、
打ち込みだけでは物足りない方は一芸加える意味も込めて練習してみたり、
楽器演奏って、へたくそでもストレス発散になりますもんね。
楽器をちょっとでもやったことあるかたなら、ギターのエフェクターを
思い浮かべると思います。あの足で踏むやつですね。
こういうの、ちなみにこれはBOSSのBD-2

ケミカルブラザーズが昔こんなのをシンセの上において使ってたりしてるのを
見たことありますが、そういうのはあまり一般的ではないです。
じゃあDTMで使うエフェクターってどんなんかっつったら
こんなの

ここで見るとすっげ小さいですが、実際は50センチくらいあるんですかね、
いわゆるラックのエフェクターですね。
ちなみに写真はALESISというメーカーの3630というコンプレッサーです。
コンプレッサーってのはいわゆる音圧を上げるエフェクターです。
「音圧ってなに?」って思う方もいらっしゃるかもしれません。
僕も上手く説明できないですが、まあブリブリにしてくれる機材です。
音が強くなる感じですね。
こういうエフェクターって高いのから安いのまでピンキリですが、
僕はこのエフェクター、結構気に入ってます。ほとんどの曲はこれかませてましたから。
安物であれ、なんであれ、通すのと通さないのでは全然違います。
ツマミをウニウニ動かしたりして、非常に楽しいのですが、
機材を色々買い揃える必要性、そして場所という問題があります。
僕も色々とサンプラーやシーケンサーを並べて曲を作っていました。
学生の時はそれでよかったのですが、会社勤めをはじめて
自分の時間がなくなってきて、それで曲を作るのにシーケンサーを
並べる時間というものは非常にモチベーションを下げてくれます。
というわけで、PCで作曲するというところに行き着きました。
で、音楽用のPCといえば、macですね。

ただ、今はwindowsのソフトも充実しています。
ROLANDのSONARなんかはWINDOWSのみ対応ってとこもあります。
僕も、macはただの迷信というか、昔の風習みたいなものだと
冷めた目で見ていたところがあったのですが、長年愛用していた
ROLAND SP-808の故障と、家のパソコン修理に出さなければならない
事態が重なったこともあって、macbookを購入しました。



で、結論。macの方が良いです。
音質とかなんとかの水掛け論がいろんなところで
繰り返されていますが、実際使いやすい。
windowsでも、ハードで作った曲をCUBASEというソフトに
取り込んでCDに焼く、とかいったことをやったりしましたが、
これで曲を作るとなるとなかなかの手間でした。
CUBASE(僕が使ってたのは廉価版ですが)


windowsが入った機種って、いろんなメーカーありますよね
僕も詳しいことはわからないのですが、機種とOSとソフトの相性って
あるらしくてですね、midiキーボードつないでもソフトシンセがどーも
上手い具合に連携してくれなかったりしました。
ちなみに僕が使ってるmidiキーボード
オーディオインターフェースもついてるので、一人二役。

それに対してmachintoshはアップルしか作ってません。
そのおかげか非常にスムーズ。接続して何の設定もなく
普通に鍵盤として機能してくれました。
あと、macのいいところとしては、garage bandというソフトが
デフォルトで入っているところです。ガレージバンドっていうくらいだから
粗雑な音楽しか作れないのかなって思ってたら、意外に良いです。
簡単だし、音色もそこそこ入ってる。
で、ステップアップするならって事でLOGIC EXPRESS

本家LOGICの半額くらいで買えます。
音色もガレバンより多いし、かなり使いやすいです。
音色もLOGICのフォーラムサイトにいくつかあったりもしますし。
使いやすい面だけではなく、パフォーマンス的にも申し分ありません。
僕が持ってるmacbookは一番スペックの低いやつなんですが、
それでもintel Core2Duo搭載です。windowsだとこの値段では
celeronが大抵です。意外にコストパフォーマンスも優れています。
とりあえず、作業で不満を感じたところは今のところ無いですしね。
前にwin機でやってたときはエフェクトが若干遅れてかかるwという現象は
度々あってました。
ただ、ウチにPC無くて、最初のPC買うんだけど・・・って人はwinの方が
いいでしょうけど。あくまでも音楽用としてですので。
CDコンポとかラジカセにつないで聴いたりするのも、ある意味大事なのですが、
音の質感とか定位などを確かめるには、リスニング環境っていうのも大事です。
ただ、スピーカーとかアンプとかって結構高いんですよね。
安くでもあるのはあるんですが、それだとどうも信頼性にかけるというか。
そんな人にオススメなのがヘッドフォンです。と
いうかモニターはヘッドフォンでやったほうがいいみたいです。ティンバランドもやってるとか。
ただここでも勘違いしちゃいけないのが、モニター用のヘッドフォンであるということ。
いわゆるリスニング用であるとか、DJ用のヘッドフォンだと、音が加工されてしまうので、
自分が作った音の素直な音がわかりません。
すると、自分の環境ではいいのに、他の環境ではあれ??というようなことにもなりかねません。
そんなわけでオススメのモニターヘッドフォン。
まずはソニーのMDR-CD900ST もうこれはド定番。
スタジオの風景なんかでもよく目にしますね。

ただ、MDR-CD900STって、すっごい耳の側でなるんですよ。
意外と疲れます。
それよりもソフトなのがこっち。
SONY MDR-7506

僕が持ってるのはこっちなのですが、ちょっと遠くで音が鳴ってる感じです。
気持ちいい感じで鳴ってくれます。
ソニーの製品って壊れやすいとかなんとか評判悪いところはありますが、
音響製品については老舗というか全体的に評判はいいみたいです。
他に評判いいのがAKGのこれ

エレクトロニカ系とかはこっちがいいとかなんとか。
ヘッドフォンは2万円以下で買えるものがほとんどですので、
スピーカーペアで7万円とかに比べればだいぶ手が届く範囲ですよね。
だから何種類か持っといても、それぞれの音質の違いなどもわかって良いです。
ちなみに僕はパイオニアのモニターなんかも持ってます。
最近の音楽って、もちろん構成であるとかメロディとかも大事ですが、
音質ってかなり重要なファクターだと思うので気を使ったほうが良いですねぇ






























